室内楽はクラシック音楽の原点
堤 剛
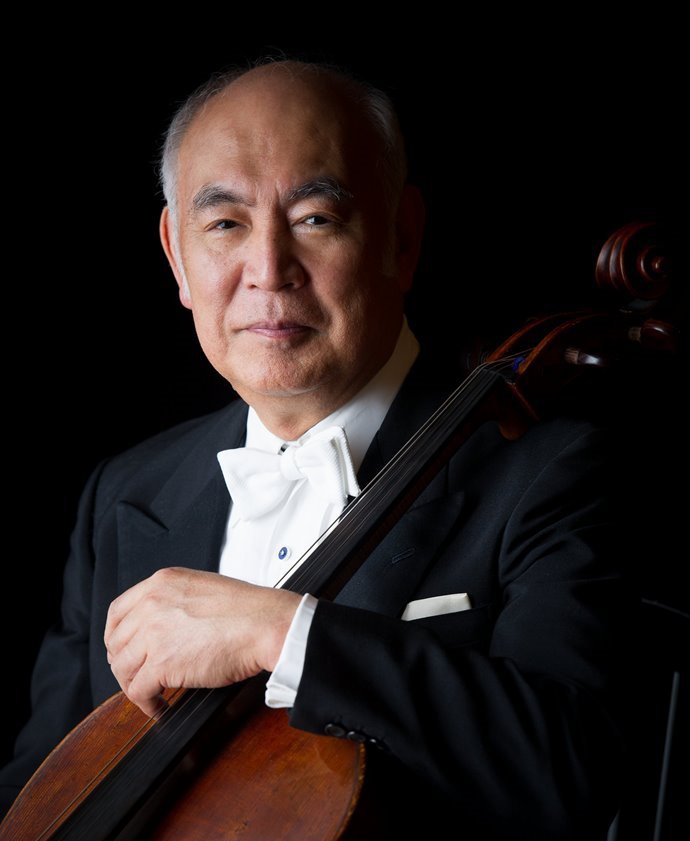
多彩な花が咲き誇る6月の室内楽の庭を、私は今年も心待ちにしています。日本にルーツを持つシューマン・クァルテットやヘーデンボルク・トリオによる、兄弟ならではの息の合ったアンサンブルは、言葉では語り尽くせない親密な響きを届けてくれることでしょう。また、世界的にも高水準のアメリカの室内楽シーンで注目を集める「イスラエル・チェンバー・プロジェクト」が今回初めて来日し、多彩な楽器編成による室内楽の魅力をお届けします。さらに、北村朋幹さんのこだわりの公演や、若手を代表する葵トリオ、クァルテット・インテグラへの期待も高く、私自身も小山実稚恵さんや若いチェリストたちとの共演を心から楽しみにしています。室内楽はクラシック音楽の原点―その喜びを、お客様との距離が近いブルーローズで分かち合えることを願っています。
堤 剛(チェロ/サントリーホール館長)
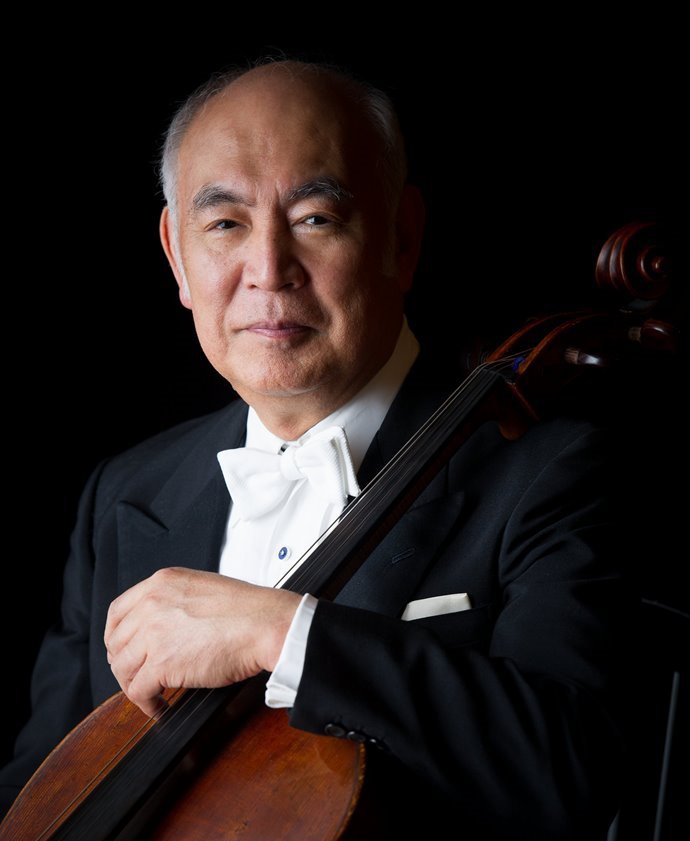

CMG2025の楽しみ方と聴きどころ
片桐卓也(音楽ライター)
◆ブルーローズ(小ホール)という庭で、室内楽の傑作が花を競う
チェンバーミュージック・ガーデン(CMG)はクラシック音楽のなかで「室内楽」と呼ばれるジャンルの作品を集めたユニークな音楽祭。まるで6月にたくさんの紫陽花や薔薇が色とりどりに花を咲かすように、ちょっと小さめのサントリーホール<ブルーローズ(小ホール)>を舞台に、室内楽の傑作が集められる。
弦楽四重奏、ピアノ三重奏といったよく知るアンサンブルだけでなく、様々な楽器の組み合わせと様々な時代の作品が集まることで、<ブルーローズ>はよりいっそう、室内楽の世界の奥深い魅力を知ることができる<庭>となる。
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲を連続して演奏する「ベートーヴェン・サイクル」もあれば、若い世代を代表するピアノ三重奏団が毎年継続して行っているシリーズもあり、ハープ2台の組み合わせから、チェロだけによるアンサンブル、そして海外からの素晴らしいゲストも、彼らの本来の魅力を花咲かせる。
午前や午後のコンサートもあり、時間も選べる点が嬉しいし、演奏家とより近い距離で音楽を楽しめる<ブルーローズ>の空間が、音楽のさらに深い感動に導いてくれる。たくさんのコンサートから自分だけの組み合わせを作り、巡ることも可能だ。

♪2025年の<ガーデン>にはこんな花たちが咲く
1)毎年ガーデン冒頭を飾る「堤 剛プロデュース」には日本の精鋭チェリストが集合
サントリーホールの館長でもある堤 剛が、毎年、アイディアを練り、チェロの魅力を教えてくれるコンサートが「CMGオープニング」。今年は上野通明、北村 陽、笹沼 樹、そして堤の4人がチェロだけによるアンサンブルを披露する。J. S. バッハの「G線上のアリア」やクレンゲルの「主題と変奏」、さらにモーツァルトの「フィガロの結婚」やフレスコバルディの「トッカータ」という珍しいチェロ4重奏版が演奏するのも注目だし、これだけの実力派チェリストが一同に会するのも楽しみだ。

2)ベートーヴェン・サイクル 〜ベートーヴェンをもっと深く知りたい時は、彼が生涯をかけて書いた弦楽四重奏曲を聴こう
CMGの名物企画となった「ベートーヴェン・サイクル」は彼が残した16曲の弦楽四重奏曲を6回に分けて、連続的に演奏する。今年は母が日本人、父親がルーマニア人というシューマン兄弟を中心とするシューマン・クァルテットがそれに挑む。6回それぞれに「Holy Song」などとサブタイトルを付け、「From the Heart」ではベートーヴェン自身の編曲による「ピアノ・ソナタ作品14-1」の弦楽四重奏用編曲も含むという意欲的な構成になった。名曲とされる「ラズモフスキー」の第1〜3番は1曲ずつに分けられ、初期〜中期〜後期の作品がバランス良く並んだ6回のコンサートは、それぞれが魅力的。しかし、全体を通して聴いてみると、きっとこれまでのベートーヴェンという人のイメージが変わって来るかもしれない。ぜひ、6回全部を通して聴いてみてほしい。

3)初出演となるイスラエル・チェンバー・プロジェクト
管楽器、弦楽器、ハープ、ピアノによるアンサンブルとして世界的に注目されるイスラエル・チェンバー・プロジェクトが初来日する。ニューヨークの有名な情報誌「タイムアウト」では「超一流のソリストの集まりでありながら、(中略)一体となって呼吸し、演奏する集合意識なのである」と絶賛される。彼らは2008年に結成され、ニューヨークとイスラエルを拠点に活動を行っている。今回の<ガーデン>では2回のコンサートを開催する。また、毎シーズンごとにゲスト・アーティストを迎えており、今年はヴィオラの赤坂智子が参加している。彼女はミュンヘン国際音楽コンクール第3位など、国際的な評価を得た後に欧米で活動。著名ソリストや世界的オーケストラとの共演も多い。
2回のコンサートの中にはブルッフ、マルティヌー、コーエン、カプレといったあまり聞き慣れない作曲家の作品も、ハイドン、シューマン、ブラームス、ベートーヴェンという作曲家の作品と一緒に並んでいる。特にマルティヌーの「室内音楽第1番」やカプレ「幻想的な物語」は聴き逃せない。そして、ヴァイオリンの小川響子(葵トリオ)、フルートの上野星矢が共演者として参加するのも楽しみである。

(右上から)赤坂智子、小川響子、上野星矢
4)ヘーデンボルク・トリオ、北村朋幹プロデュースなど、ここでしか聴けないコンサートも
コンサートの数が多いので、どうしても全部には行けないという方には、この<庭>でしか味わえない、特別なコンサートに注目していただきたい。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートにも弦楽器奏者として出演していたヘーデンボルク・和樹(ヴァイオリン)、直樹(チェロ)と、その兄弟である洋(ピアノ)の3人によるヘーデンボルク・トリオは、彼らの暮らすウィーンで活躍したベートーヴェンとシューベルトの「ピアノ三重奏曲」を演奏する。音楽の伝統の中に生きる姿を間近に感じることができるはず。

気鋭のピアニストである北村朋幹はこれまでも彼自身のアイディアによるコンサートを企画して来たが、今年はシェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』を取り上げる。ソプラノの中江早希を迎えるほか、郷古 廉(NHK交響楽団第1コンサートマスター)、横坂 源(チェロ)、岩佐和弘(フルート)、山根孝司(クラリネット)という実力派のメンバーを集め、ドビュッシーとシェーンベルクによる作品を演奏するのは、まさに一期一会の体験となるだろう。

5)午後の短いコンサートと華やかなフィナーレも
お昼のゆったりした時間に1時間ほどの短いコンサート「プレシャス1pm」を開くのも<ガーデン>の魅力。堤 剛と小山実稚恵がショパンとブラームスのチェロ・ソナタを共演。またもうひとつのコンサートでは世界的なハープ奏者である吉野直子とマリー=ピエール・ラングラメが、ダマーズ、ナデルマンなどの珍しいハープ2台のための作品で彩りを競うのが素敵だ。

全体の最後に待っている「CMGフィナーレ 2025」は、今年の<ガーデン>に参加したアーティストのほかに、サントリーホール室内楽アカデミーのファカルティとして活躍する元・東京クヮルテットのメンバーである原田幸一郎、池田菊衛、磯村和英、そして毛利伯郎も参加。もちろん堤 剛も参加して、豪華なメンバーが競演する。世代を超えて集う音楽家たちの出会いは、また新しい感動をもたらしてくれるだろう。

♪「庭」をどこから眺めるか? その視点も、歩き方も自由自在。
自分で作る室内楽の世界が、そこに現れてくる
1)家族で作るアンサンブル=室内楽はそこから始まった?
そもそも室内楽は比較的親しい人たちのなかで演奏されて来た歴史がある。特にヨーロッパでは家族で室内楽を演奏することも多かった。その歴史を体現しているようなグループが、シューマン・クァルテットとヘーデンボルク・トリオ。いずれも母親が日本人で、ヨーロッパで育った兄弟によるアンサンブルである。日本でも兄弟姉妹の演奏家は多いけれど、一緒にアンサンブルを作っている例は少ない。やはりそこにはヨーロッパの伝統が流れている。

2)気鋭の若手演奏家が集まる
最近の<ガーデン>の特徴として、日本で注目を集める若手演奏家がみずからコンサートをプロデュースすることが多くなっている。『月に憑かれたピエロ』は昨年に小菅優(ピアノ)も取り上げた作品なので、北村朋幹が今年も取り上げることで、2年にわたっての聴き較べもできる。若い演奏家の意欲が<ガーデン>に新しい色を添える。

3)ベテランから若手への「音楽伝統の継承」
サントリーホールは室内楽アカデミーを主宰し、現在は第8期となる(注・1期2年)。そこから巣立ったクァルテット・インテグラ(第5・6期に在籍)と、アカデミー時代の先生であった練木繁夫との室内楽は、先生と弟子という枠を超えた共演のなかで、先行する世代の経験と知識が若い世代に受けつがれる、ひとつのラボラトリーのような面を持っている(クァルテット・インテグラ×練木繁夫)。やはり室内楽アカデミーから生まれた葵トリオ(3人とも第3期に在籍)の演奏にも、先行世代から受け取ったサムシングを感じることができるだろう。
そして現在室内楽アカデミーで学ぶ8期生たちの「室内楽アカデミー・フェロー演奏会」は午前11時開演で、今年は上野星矢(フルート)も参加する。ぜひ、未来を作る若い演奏家たちの勢いを感じてほしい。

4)CMGスペシャル「チャレンジド・チルドレンのための室内楽演奏会」
これも毎年行われているコンサートで、生の演奏に触れる機会の少ない特別支援学校に通うこどもたちを招いた(招待のみ)特別なコンサート。世界的なヴァイオリニスト・渡辺玲子がプロデュースしており、開かれた音楽の<庭>としてのCMGの一面を担っているコンサートである。

5)幅広い世代の作曲家たち、未知の作品の発見も<庭>ならではの風景
普段のオーケストラ・コンサート、ソリストのリサイタルでは見つからないような未知の作曲家による作品も2025年はたくさん演奏される。ハープの吉野直子&マリー⹀ピエール・ラングラメによるダマーズ、ナデルマン(プレシャス 1 pm)、葵トリオの「7年プロジェクト第5回」にはマルティヌーの「ピアノ三重奏曲第2番」が登場し、イスラエル・チェンバー・プロジェクトでは、ベートーヴェンの傑作交響曲、第3番「英雄」が室内アンサンブル用編曲で演奏されるのが注目だ。楽器の意外な組み合わせで音楽の印象が変化する作品も多く、新しい魅力を発見できる作品もたくさんあるはず。花の中に埋もれた宝石を探すように、そうした発見の楽しさをこの<ガーデン>で体験していただきたい。
