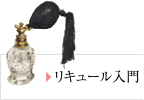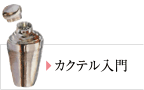イギリスでは夏に飲まれるカクテルを、日本では冬から早春にかけて味わうことになる。材料にいちごを使うからだ。
テニスの四大大会の一つであり、1877年に第1回大会が開催された古い歴史を誇るウィンブルドン選手権(Wimbledon Championships/当初は男子シングルスのみ)は、いちご無くしては語れない。報道で“ウィンブルドン開幕とともにイギリスの夏は正式にはじまる”といった表現が使われたりするが、いちごもまた夏の到来を知らせる旬の食べ物として大会観戦の風物詩となっている。
大会は毎年6月の最終月曜日から2週間の予定で、ロンドンはウィンブルドンのオールイングランド・ローンテニス・アンド・クロッケー・クラブ(All England Lawn Tennis and Croquet Club)で開催される。日本人の若い人たちのなかに、なんでいちごが6月から7月にかけてのこの時期なのか、と奇妙に感じられる人がいても不思議ではない。
日本でいちごが出回るのは11月頃から4月頃まで。品種にもよるが1月から3月にかけてのものがいちばん美味しいとも言われている。
かつては日本のいちごの季節は4月から6月頃だった。1970年代まではそうであったとわたしは記憶している。ところが露地栽培からビニールハウス栽培に切り替わり、品種の改良、開発もすすみ、日本のいちごはとても魅力的な味わいとなっていった。
ご存知の方は多いと想う。理由はクリスマスにある。洋菓子メーカーのマーケティング戦略によって、白い生クリームに赤いいちごが乗っかったケーキでクリスマスを祝うシーンが定着していく。これにより年末にいちごの需要が急増したためにハウス栽培へと切り替わり、収穫期が大幅に移動したのだった。
ちなみに俳句の世界では、いちごの季語は初夏(5月頃)である。
余談。日本にはショートケーキの日というものが毎月あるらしい。22日に制定されている。何故か。カレンダーを見ていただきたい。毎月22日の上には必ず15日、そう、“いちご”が乗っかっている。
ウィンブルドンに話を戻そう。開催期間中、いちごは毎朝、手摘みで収穫されて会場に配達される。キャサリン妃がへた取りを手伝った、といった報道が流れるなか、関わるケータリングスタッフは1,600人を数える。
消費される量は尋常ではない。約38トン、200万個以上になるらしい。一個ずつ並べていくと40マイル、約64キロにおよぶという。東京駅を起点にすると、東は成田、西は平塚あたりになるはずだ。
名物は「ストロベリー&クリーム」。日本ほどいちごは甘くないらしく、カップに10粒程度入れてダブルクリームと呼ばれる脂肪分の高いクリームをたっぷりとかける。なんと第1回大会から会場で販売されていたという。毎年変わることなく、観戦者はこれを楽しみにしている。
また、シャンパンを飲みながらいちごを味わう光景も見られる。さらにはいちごを使ったカクテルも大会を盛り上げる。

ご紹介するのは「ウィンブルドン・マティーニ」。1990年代に登場したらしいのだが、それ以上の詳細を伝える情報にはまだ出会えていない。
材料はホワイトラム、ストロベリーリキュール、シュガーシロップ、生クリーム(シングルクリーム)にいちご3個。「ストロベリー&クリーム」をイメージして生まれたカクテルに間違いはないだろう。色調からよく知っている味わいが想像でき、期待を裏切ることはない。
今回はイギリスでのレシピをそのまま伝えるが、日本では数字通りにはいかないかもしれない。日本のいちごはしっかりとした甘みがあり、ストロベリーリキュールも味わいに貢献しているので、シロップは1ティースプーンくらいに、あるいは必要ないという人もいるかもしれない。
三角形の大ぶりのマティーニグラスを使い、縁にいちごを飾るスタイルが基本らしい。その通りに試してみたが、なんだか間が抜けた感じでよろしくない。グラスはもっとチャーミングなものがいい。
生クリームに関しては少し勉強した。イギリスをはじめアメリカなど、生クリームを扱うレシピでダブルとかシングルといった表記をよく見かける。パティシエの方々にとってはそれがどうしたの、ってことになるかもしれないが、わたしはこれまで、なんのこっちゃ、と首を捻りながらも特別に取り上げるようなカクテルがなかったためにスルーしてきた。
でも、「ウィンブルドン・マティーニ」について語ろうとするとイギリスの表記に準じることになる。このカクテルにおいてはシングルクリームと明記された文献がとても多いのだ。
調べてみると、ダブルクリームは乳脂肪分約48%の濃度の高い、こってりコクのあるクリームで、日本でパック売りされている生クリームはこれに近いという。シングルクリームは泡立てても固まらない脂肪分約18%の軽いもので、コーヒーや紅茶に入れて味わうのにいい。
イギリスではホイッピングクリームという脂肪分約36%のものが存在している。その名の通り、ケーキのデコレーション用に泡立てて使うにはこちらが適しているようだ。
スコーンに添えられているのはクロテッドクリーム(clotted cream)という。これをスコーンに塗って食べるととても美味しい。乳脂肪分約55%の濃厚な、熱処理されているクリームだ。
ウィンブルドン選手権に関連するカクテルを紹介しながら、ここまでまったくテニスに触れないで語ってきた。テニスに関心がない訳ではない。わたしの学生時代はサーフィンやスキー、そしてテニスが人気で、すべてをたっぷりと楽しんだ。とても幸せな時代だったといえる。バイトで金を稼いでは、真剣に遊んでいた。
日本でもテレビでウィンブルドン選手権をライブ観戦できるようになっていたが、衛星中継事情がまだよくなくてやたら画面が乱れた。中継断もしばしば起こり、“しばらくお待ちください”のテロップを苛つきながら見つめていた。
その頃のスター・プレーヤーは、男子はビヨン・ボルグ、ジミー・コナーズ、そしてジョン・マッケンローなど。女子ではマルチナ・ナブラチロワとクリス・エバートだった。とにかく、とても古い時代の話だ。
いまもテレビ観戦するが、肩入れするプレーヤーはいない。ウイスキーのハイボールを飲みながらの観戦である。もちろん、いちごはない。