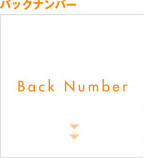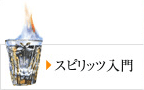輝かしい時代の到来を告げる「ゴールデン・ドーン」(Golden Dawn/黄金の夜明け)という名のカクテルがある。100年近く前に世に出たようなのだが、名前ほどには華々しく流行した記録がない。
アメリカがまだ禁酒法下(1920−1933)にあった1930年、イギリス・ロンドンで国際的なカクテルコンペティションが開催され、その時の優勝カクテルが「ゴールデン・ドーン」であったと伝えられている。
創作者はトム・バタリー(Tom Buttely)。ロンドンの名門ホテル、ザ・バークレー(The Berkeley)のヘッド・バーテンダーだった。
ザ・バークレーの歴史は古く、はじまりは1700年代であるという。ピカデリーストリートとバークレーストリートの角に位置していたグロスターコーヒーハウス(The Gloucester Coffee House)が起源である。
そのコーヒーハウスはロンドンから南西へ向かう郵便馬車の御者たちの拠点であった。やがて旅籠となり、拡張、発展してロンドン発着の郵便馬車利用者のためのホテルとなる。鉄道の発達とともに1897年には正式にザ・バークレーと改名した。現在、ハイドパークの南、素敵なブティックが軒を連ね、高級住宅街でもあるナイツブリッジに位置するザ・バークレーは、1972年に移転して建てられたものらしい。
そしてトム・バタリー。現段階では彼についての詳細を語った文献に出会えていない。「ゴールデン・ドーン」は『Café Royal Cocktail Book』がカクテルブック初出のようだ。この連載で何度か紹介している一冊で、イギリス・バーテンダー・ギルド(UKBG)が1937年に刊行したものだ。
そのレシピ記載箇所には“Invented by the late Tom Buttely”とある。つまり、1937年にはすでに故人となっていた。
バタリーがUKBGの会員であったとする文献がある。UKBGが発足したのは1934年。設立初期の会員ということになり、そしてまもなくに他界したことになる。「ゴールデン・ドーン」が話題にならなかったのはそれ故なのか。彼がバークレーのホテルバーでカクテルをつくりつづけていたならば違っていたのではなかろうか。わたしが気にかかっている部分はそこだ。
とても美味しくて、しなやかなフルーティーさにあふれている。それなのに地味な存在でありつづけてきたのは何故なのだろうか。
レシピは、ジン、カルヴァドス、アプリコットリキュール、オレンジジュースを同量でシェークしてカクテルグラスに注ぎ、グレナデンシロップを沈めるというものだ。グラスの底がほんのりと赤く染まる。
後に登場してくるロングドリンクの「テキーラ・サンライズ」のスタイリングは、「ゴールデン・ドーン」をモチーフにしたのかもしれない。
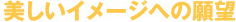
1927年、ミュージカル「ゴールデン・ドーン」がニューヨークのブロードウェイで上演され、トム・バタリーがカクテルコンペで優勝した1930年にはハリウッドで映画化されている。
プロットを見ると、物語は東アフリカを舞台として、第一次世界大戦時のドイツ兵、イギリス兵、現地住民の関係を描いている。人種問題を憂慮すべき描写がかなりある。
ドイツ軍はイギリス軍捕虜をゴム農園で働かせ、捕虜たちが地元のバーに通うことを許している。バーを経営するのは現地女性で、その娘はドーンという名の白人である。彼女は幼い頃に誘拐されたらしい。こんな設定で、イギリス人捕虜とドーンの恋があり、ドーンが現地人によって神の生贄にされそうになったりする。
インターネットで海外のサイトを調べてみると、わずかながらカクテル「ゴールデン・ドーン」とこのミュージカルを関連づけて語っているものがあるが、わたしはそうは想えないし、想いたくもない。ハッピーエンドであるにしろ、たまたまバタリーのカクテルコンペ優勝と映画化が同年であったからなのではなかろうか。
もうひとつ、年代を遡った1887年。ロンドンで西洋魔術結社『黄金の夜明け団』(Hermetic Order of the Golden Dawn)が設立している。儀式魔術を実践する秘密結社で中産階級を中心に影響力を持ったが内紛が起こったようで、1903年には消滅している。
ここからはわたしの推測であることをご理解いただきたい。19世紀末の秘密結社、そして第一次世界大戦後のアメリカでの舞台や映画によって、「ゴールデン・ドーン」という名は当時のイメージとして決して喜ばしいものではなかったのではなかろうか。カクテル創作者が早くに逝去したこともあるだろうが、輝かしいとはいかないまでも、それなりの人気を得られなかった理由はここにあるのではなかろうか。
それでも今日まで地味というか密やかにカクテル「ゴールデン・ドーン」が知られてきたのは何故なのか。1930年代以降、ほとんど話題にならなかったようだが、長きにわたりアメリカのバーテンダーたちに愛されつづけている『Mr. Boston Official Bartender‘s Guide』の1974年版に登場したことが大きいといわれている。
とても美味しい、と先述した。リンゴからつくられるブランデーとアンズのリキュールの相性がよく、そこにオレンジジュースがとても自然に溶け込んでいる。ジンは力強さのあるクラフトジン「シップスミス ロンドン ドライジン」を選んでみた。しなやかなフルーティーさが口中に広がるなか、後口に「シップスミス」のボタニカルのスパイシーさがほんのりと浮かび上がり、柑橘系のほのかな酸味も感じ取れる。
ただのフルーティーではない複雑味がある。
調べていくなかで、1930年という節目、新たな年代が輝かしい時代になるようにとの願いを込めたネーミング、と書いた文献もあった。わたしもそう想いたい。前年、1929年から世界恐慌に見舞われているなか、ミュージカルの重苦しい話を基にカクテルを考案するとは想えない。
このエッセイを書く直前、バラに詳しい知人に期待する訳でもなく、まったくの思いつきで「ゴールデン・ドーンって名前のバラはありますか」と聞いてみた。すると「あるよ。素敵なバラだよ。ネットで調べたらすぐに出てくるはずだ」と教えてくれた。
画像を見ると、淡い黄色を主体に滲んだように薄いピンク色に染まった花弁が印象的で、とても品がある素敵なバラだった。しかも作出はオーストラリアで1929年とある。そうだよ、これだよ。
真実は不明。でも、輝かしい未来を謳った美味しいカクテルなんだからイメージは美しくありたい。勝手ながら、トム・バタリーはカクテルコンペの前年に誕生したバラからイメージして考案した、と想いたい。
酒は楽しく味わいたいじゃん。