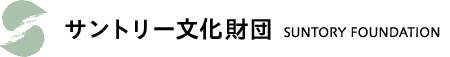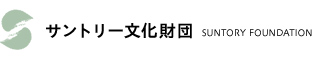受賞のことば
社会・風俗2025年受賞
『米原昶の革命 ─ 不実な政治か貞淑なメディアか』
(創元社)
1985年生まれ。
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。
日本学術振興会特別研究員(DC1)などを経て、現在、東京経済大学コミュニケーション学部准教授。
著書 『昭和50年代論』(共著、みずき書林)など。

物心ついたときに冷戦は終結しており、ぼんやりと抱きしめてきたパクス・アメリカーナは9.11テロで打ち砕かれる。16歳、高校生だった私は進路選択に窮した。「自己の小さな物語と世の中の大きな物語とが交差する夢」(米原万里)の座標が激しく揺らいだこの時、ただ環境に適応するまま、ものを考えず生きてきたことを痛感した。田舎の進学校で焚き付けられた「身をたて 名をあげ」の気風のみを内面化し、京都でそぞろ学んだ。大学院に進学すると、3.11に遭遇する。少なからぬ仲間が大学を去り、それぞれ現場を持って“革命”に邁進した。安全地帯から後方支援に留まる自分には、後ろめたさが付きまとった。
米原昶(いたる)(1909-1982)の評伝を書く、という好機がめぐってきたとき、その覚悟を支えたのは、若い頃に持て余し腹の底で燻っていた地方出身学生のエートスだったように思う。私たちはどこから来たのか。あの歌をかいた「先輩」とは何者か。明治の末、鳥取の旧い村の山林地主に生まれた次男坊で、県下随一の中学では大正デモクラシーを謳歌し、昭和の初め第一高等学校で革命運動に目覚める。命の危険さえ伴う治安維持法の時代を生き抜き、転向なきまま、戦後は日本共産党の代議士として奮闘する「家事するお父ちゃん」の軌跡を、今を生きる同世代に宛てて綴った。私たちはどこへ行くのか。混沌とする未来に向き合うには、歴史という道標が必要だ。
米原昶とその時代は、私たちと、かくも異なる。例えば、その耳。難聴に苦しんだ右耳は、自己鍛錬を徹底する一高柔道部の荒稽古が原因だ。頼りにした左耳は、良家ゆえ享受できた治療の賜物である。格差社会とエリートの生き様の痕跡がみえる。例えば、その山。手入れされた故郷の樹木は、50年、100年、200年の尺で物事を捉える視野と、広く、篤く、息の長い人間関係のあり方を象徴する。具体的な足取りを探るべく、できる限り、ゆかりの地を歩いた。設計図なき石積みのような執筆作業では、豊かな出会いに恵まれた。
共産主義というイデオロギーではなく、「メディア政治家」の視点でその生涯を読み解いたことも、筆の自由を格段に広げた。新聞も雑誌も「紙」であった時代、議員として、機関紙編集長として昶が取り組んだ政策の追究は、素材から配達、販売、流通の観点でメディアを論じる未開拓領域の発見でもあった。この度の受賞は、メディア史研究という方法の可能性に対していただいたものだと受けとめている。導いてくれた共同研究者に深く感謝したい。
気の遠くなるような栄えある賞と、ささやかな自分との間で、これからどのように言葉を紡いでいくのか。張り詰めた思いで自問し、呼吸し、じっと手を見る。まずは、集めた石をコツコツと積みあげていきたい。