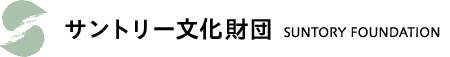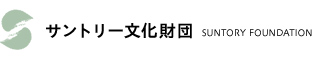受賞のことば
芸術・文学2025年受賞
『無意味なんかじゃない自分 ─ ハンセン病作家・北條民雄を読む』
(講談社)
1980年生まれ。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。東京大学大学院人文社会系研究科付属次世代人文学開発センター特任研究員などを経て、現在、二松學舍大学文学部教授。
著書 『凜として灯る』(現代書館)など。

私が北條民雄(1914-1937年)と出会ったのは、彼の享年と同じ23歳の時でした。2000年代初頭のことです。あの頃、北條が暮らしたハンセン病療養所(国立療養所多磨全生園:東京都東村山市)には戦前の療養所を知る古老がまだ幾人もご健在で、中には北條と面識があったという人もいらっしゃいました。今から思えば、こうした証言者と出会える時間的に最後のチャンスだったのでしょう。古老たちの肉声を通じて聞く昔話は、私にとっては北條の小説よりも刺激的でした(こんなことを書くと北條に怒られそうですが……)。
かつての療養所では、患者たちによって様々な自助・互助の活動が行われていました。自分たちが生きるために必要なものを自らの手で作り出していく営みがあったのです。お世話になった古老の一人は、それを「隔離の文化」と称していました。本書で紹介したハンセン病文学もその一例でしょう。
北條民雄も隔離という極限状況を生きることの意味を問い、命燃え尽きるまでペンを走らせ続けました。その意味では、彼の創作活動も「隔離の文化」の一つだと思うのですが、北條は自分の文学を他の患者のそれと一括りにされることに強い嫌悪感を持っていたので、私にこのように書かれることを拒絶するでしょう。以前の私は彼のこうした激情が苦手でしたが、今回本書を書くにあたって久しぶりに全集を読み直してみると、その刺々しさがなぜか愛おしくさえ感じられました。私が歳を取っただけかもしれませんが。
私はハンセン病文学の研究を通じて、次のようなことを学びました。――苦しくつらい境遇に追い込まれた人は、時に自分を照らし温めるための火を自らの手でともすことがある。だとしたら、人間存在にとって切実なその営みの意義を追い求めたい。古老たちの語りを卓袱台ごしに伺うことを重ねるうちに、こんな身の丈に合わない決意をしてしまいました。
あれから20年と少しの時間が経ちました。その間、いくつかのプロジェクト(自分の中での研究構想)に取り組み、ハンセン病以外のフィールド(障害者文学、障害者解放運動、精神科病院でのアート活動、ウーマン・リブ)にも飛び込み、いく冊かの本を書き継いできました。傍目には、手あたり次第、行き当たりばったり本を書く学者に見えているかもしれませんが、私の中では一貫して「自らの手で火をともす人」を追いかけ続けてきたつもりです。
今回、私の原点である北條民雄の評論で本賞を賜り、自分が問い続けてきたことが間違ってはいなかったのだと強く励まされたように感じています。今後も、ぶれず、揺るがず、焦らず、たゆまず、私なりの歩幅で「自らの手で火をともす人」を追い続ける所存です。