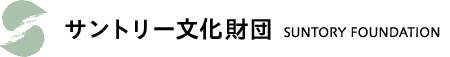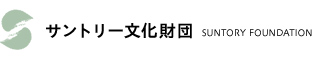選評
芸術・文学2025年受賞
『無意味なんかじゃない自分 ─ ハンセン病作家・北條民雄を読む』
(講談社)
1980年生まれ。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。東京大学大学院人文社会系研究科付属次世代人文学開発センター特任研究員などを経て、現在、二松學舍大学文学部教授。
著書 『凜として灯る』(現代書館)など。

荒井裕樹氏の『無意味なんかじゃない自分』は、そのくだけたタイトルから内容が想像しにくいが、副題にもある通り、「ハンセン病作家」として知られる北條民雄の著作を読み直す試みである。サントリー学芸賞の最近の候補作の多くが、新進の若手研究者による博士論文に基づいた「硬い」学術書であるのに対して、本書は柔らかな「です・ます」調で書かれた長編エッセイという趣があり、その意味では異色作と言えよう。平明な達意の文章は読みやすく、説得力がある。
とはいえ、決して手軽に書かれた読み物ではない。背後には著者の長年の学術的研究と社会的実践の重みがある。荒井氏は、ハンセン病者と脳性麻痺者の文学活動を扱った博士論文「病者と障害者の文学における自己認識と自己表現の諸相」(2009年)を出発点とし、その後も一貫して障害者文化論に取り組んできた。本書はそういった著者の思想の到達点を示すものになっている。
北條民雄(1914-1937)は、ハンセン病の療養所に隔離されながら創作を続け、23歳で亡くなったが、代表作「いのちの初夜」(1936年)は病苦と差別の苛酷な極限状況で「いのち」の輝きを見つめた類例のない作品として記憶されている。しかし今では、「あまりにも高くて遠いところに」祭り上げられてしまった感もある。荒井氏は北條を、一人の青年として「体温と息遣いが感じられるくらいの距離に置き直」す。そして、彼の著作や言動に認められる、周囲の人々に対する傲慢さや毒々しさから目をそむけず、そのような態度を取ることがはたして「認められる」のか、と問いかける。これは実証的な研究にはなじみにくい優れて倫理的な問いだが、このような問題意識から荒井氏は現代社会に蔓延する「生きにくさ」という大きな話題にも議論を接続していく。
その一方で、本書は厳密にテクストに向き合うことがいかに大事かを教えてくれるという意味では、伝統的な文学研究のよき手本でもある。「いのちの初夜」に出てくる「バット」(煙草の銘柄「ゴールデンバット」の略称)というディテールの深い意味や、日記の筆写の際に行われた改竄に秘められた人間関係などを解き明かすくだりには、わくわくさせられた。
障害者・病者に対する社会的な差別・偏見から、苛酷な境遇に置かれた個人の痛々しい自意識まで。提起されるのは単純には答えられない複雑な問題ばかりである。しかし、荒井氏は安易な答を出すことは避け、むしろ問い続けること、そして問いの「解像度」をあげることが大事だと説く。じつはこのようなネガティヴ・ケイパビリティ、つまり解決できないことをそのまま受け止めて向き合い続ける能力こそ、今日の人文研究、特に本来要約できない複雑な現象である文学作品の研究に必要なのではないか。今の世の中、まず明確な「アーギュメント」(主張)を示し、切れ味のいい理論を使ってそれを理詰めに立証するといったタイプの論文をよしとする効率主義の風潮が強まる中、このような姿勢は貴重である。
すでに数多くの優れた著作のある荒井氏ではあるが、今後も引き続き障害者文化研究という大事な分野を牽引し、さらに社会的発信を続けていかれることを期待したい。
沼野 充義(東京大学名誉教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)