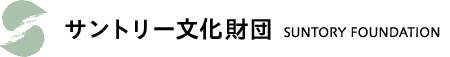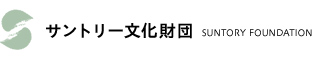受賞のことば
思想・歴史2024年受賞
『近代チベット政治外交史—清朝崩壊にともなう政治的地位と境界』
(名古屋大学出版会)
1980年生まれ。
筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・人類学専攻(博士課程)修了。日本学術振興会特別研究員などを経て、現在、九州大学大学院比較社会文化研究院准教授。
著書 The Resurgence of "Buddhist Government"(共著、Union Press)

チベット仏教は歴史上、ヒマラヤ・チベット地域のみならず、モンゴルやマンチュリア、北京にまで波及し、ユーラシア東部の歴史を動かす要因となってきました。その総本山であったチベットにおいて、20世紀中頃まで広大な領域を統治し続けたのが、政教一致の体制をもつダライ・ラマ政権(1642-1959)でした。
地域や民族を超えた宗教権威と、その政治体制の個性ゆえに、ダライ・ラマ政権は他の諸地域と比べても、近代国際秩序に合致した国家の体裁を整える上で一層大きな困難に直面したと言えます。その一方で、列強や中国も、ダライ・ラマ政権の判断や行動をコントロールできてはおらず、外交交渉や境界紛争においてダライ・ラマ政権は周辺大国とせめぎ合いを続けました。本書は、中華人民共和国による併合以前においてチベットが辿った複雑かつ濃密な歴史を、その政治的地位と境界の「未確定」という問題に焦点を絞り、ダライ・ラマ政権の模索の過程に即して検討しました。
ただし、書き終えて改めて感じたのは、20世紀中頃までのアジア各地の国家形成において「確定」していた要素など、実はほとんど無かったのだろうということです。流動的な国際情勢下におけるチベットの選択と経験の一端を論じた本書が、個別の地域研究を超え、現代アジアの原型・起源を探る上での素材となるならば幸いです。
日本には、私の専門領域である東洋史学を含む歴史学、さらにはチベット学の重厚な蓄積があります。本書もこれら先行する業績から多大な恩恵と啓発を受けており、このことに深く感謝しています。その一方で、近代チベット史については、国内での研究者が少なく、海外の学界が牽引しているという現実がありました。こうした中で、この分野が抱える史料的制約の克服に挑み、新たな手法や論点を探し、国内外で研究成果を伝えることは、やりがいはあったものの、いつも困難と迷いを覚えていました。このたび栄誉ある賞を頂き、自身の取り組んできたことはそれほど間違いではなかったのだなと実感することができました。本当にありがとうございます。
本著のテーマと関わりながら、論及できなかった課題は多くあります。例えば、第二次世界大戦、国共内戦、インド独立と連動しつつ、チベット史は新たな展開を見せていくのですが、本書はその1940年代以降の歴史を検討できていません。さらにチベットには、ユーラシア中央部の高原で近代世界から「孤立」していたイメージがつきまとうと思いますし、今日のチベットが抱える政治的課題もあり、その歴史は一層わかりづらいものとなっているでしょう。本書を私の研究の新たな出発点と捉え、近代チベット史をアジア各地域の歴史研究との比較・対話・接続が可能なかたちで描いていく必要があると一層感じています。また、今回の受賞が、時代を問わず、チベット史・チベット学自体に注目が集まる新たなきっかけになり、研究を志す方が登場することを念願しています。