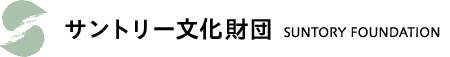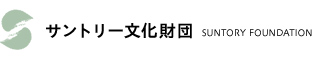選評
思想・歴史2024年受賞
『近代チベット政治外交史—清朝崩壊にともなう政治的地位と境界』
(名古屋大学出版会)
1980年生まれ。
筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・人類学専攻(博士課程)修了。日本学術振興会特別研究員などを経て、現在、九州大学大学院比較社会文化研究院准教授。
著書 The Resurgence of "Buddhist Government"(共著、Union Press)

わが家には仏壇がある。だから僧侶がお経をあげ、家人がお布施をするのは、毎月のあたりまえではあった。そんな寺院と檀家に、上下も優劣もない。寺の切り盛りは住職の裁量だ。ところがある日突然、ある檀家が寺院の区画から経営まで、西洋じこみの法律で一切とりしきると決め、よろず言うことを聞けという。住職はじめ、お寺こぞって周章狼狽、近隣の人々に助けを求めた。これまたあたりまえの展開かもしれない。
20世紀初めからこのかた、チベット・中国の関係史を前者の目線で、下世話に言い表すとこうなる。もちろん卑近に失し、論理にも解説にもなっていない。しかしこの関係を学問的に論証するのは、ほぼ不可能だった。
当時のチベット仏教と中国政治に対する乏しい理解、現在もつづく亡命チベット政府の運動と中華人民共和国の政策、さらには言語習得の困難、史料と知識の偏在など、すべてが前途にたちはだかる。
下世話な説明でお茶を濁すか。それが論外だとすれば、学術的に寺院の理念と言い分を精細に明らかにするか、さもなくば、檀家の経歴と変容をつまびらかにするか。いわば二者択一が関の山だった。
つまり前者はチベット学、後者は中国史学に相当する。いずれも日本の研究は世界最高水準とはいえ、両者は必ずしも切り結ぶことなく、なかんづく関係の転換を学術的に解明するには限界があった。
敢然と択一を拒否し、限界に立ち向かったのが、著者の研究である。チベット学の蓄積を背景に、チベットをめぐる政治的動向を跡づけつつ、同時に中国史研究の成果を生かして、ダライ・ラマ13世政権の政治外交の復原に成功した。当時の日本との関係にも、探究の目配りを怠らない。
西洋由来の「国民国家」「領土主権」概念のもと、支配をすすめる清朝・中国こそ、チベット最大の脅威と化す。英領インド・西洋に対する依存は、欧米の煽動・誘掖ではなく、ダライ・ラマ自身の意思・選択だった。
この20世紀初頭の転換が、東アジアの歴史と現代を分かち、そしてつなぐ出来事である。なぜチベットが現在のような政治的地位なのか、中印国境が定まらないのか、中国の民族問題が解決しないのか。その淵源をなす歴史過程であり、本書がおよそ世界ではじめて実証的、客観的に描き出した。
外交史を研究するには、各国各地の外交文書を探索解読する、いわゆるマルチ・アーカイヴァル・アプローチがあたりまえである。しかし時に、これが難しい。閲覧不可能な史料があるのは歴史学で当然ながら、亡命チベット政府の前身たるダライ・ラマ政権の政治外交関連文書はその最たるものだろう。系統的にまとまって入手、閲覧するすべはない。著者は各国各地に散在するチベット語史料を蒐集し、あわせてその所在のゆえん、ひいてはその国との関係を考察するなど、多角的な調査を通じ、ようやくあたりまえを実現させた。
あたりまえを習い、疑うのが学問の基本である。しかし何事も基本に徹するのが難しい。実践できた研究こそ非凡である。本書はそんな非凡の所産ながら、それで終わりではない。非凡をあたりまえに還元する作業が残っている。冒頭の下世話な話法に代わる一般的な論述こそ待ち遠しい。著者にしかできない任務になろう。
岡本 隆司(早稲田大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)