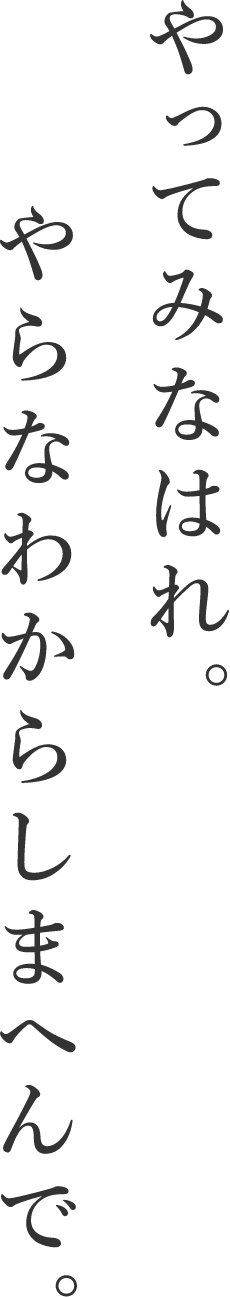
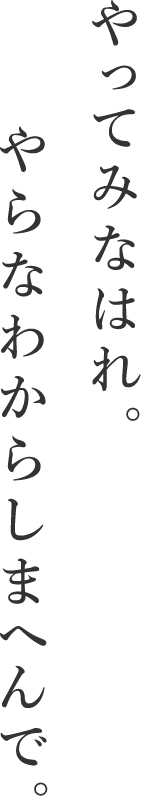
創業者 鳥井信治郎は未知の分野に挑戦しようとして
周囲から反対を受けるたび、この言葉を発して
決して諦めなかったという。
開拓者たる覚悟と責任を問うこの言葉は、
時代を超えてサントリーグループのDNAとなり、
社員一人ひとりの次の一歩を後押しするドライブとなっている。
サントリーグループは真のグローバルカンパニーへと
飛躍する転換点にいる。
多様な考え方や背景をもつ人々が集い、新しいビジネスを
展開することで、新しい価値が生まれる。
今こそ歴史を振り返り、サントリーの根底に流れる
「やってみなはれ」の本質に目を向けるべきだ。
初代社長の口癖だった「やってみなはれ」を、
歴代の社長はどう継承し、実践したのか。
「やってみなはれ」の源流を探る。
1899年、創業者・鳥井信治郎は独立し「鳥井商店」の看板を掲げた。当時洋酒はごく一部の人々が薬として葡萄酒をたしなむ程度で、庶民には馴染みのないものだった。そんな中、本場の葡萄酒の美味しさを知った信治郎はスペインからの輸入葡萄酒を売り出す。しかし渋く酸味も強すぎるとして商売は大失敗に終わった。それでも信治郎は打たれるほど闘志を燃やした。試作に次ぐ試作の末「赤玉ポートワイン」が完成、好評をもって市場に迎えられた。
「世界のどこにもない、日本のぶどう酒や」

(出典:「まかせて伸ばす」
鳥井信一郎編著)
リキュール用アルコールが発酵し偶然できた「トリスウイスキー」が評判を呼んだことで「日本にもいつかウイスキーの時代がくる。自分の手でウイスキーをつくりたい」と志す。
周囲は猛反対したが、 「自分の仕事が大きくなるか小さいままで終わるか、やってみんことにはわかりまへんやろ」と赤玉ポートワインの利益のほぼすべてを国産ウイスキー製造につぎ込んで挑戦した。
根底には「洋酒報国」への信念もあった。日本人に受け入れられるウイスキーをつくり、洋酒の輸入金額を半分にすることで、急速な近代化を目指す日本の一翼を担いたい。また、洋酒に志をたてた以上、ウイスキーをやらねば本物ではないとの思いもあった。
「わしがウイスキーをつくるのは、日本の事業家が誰一人手を出そうとせんからや。日本でもウイスキーがつくれることを実証したいんや」

初代社長鳥井信治郎は、商品化に時間のかかるウイスキーと製造期間の短いビールの2本柱による経営を意図し、赤玉ポートワインで得た資金をもとに日英醸造(カスケードビール)を買収した。そして1930年「オラガビール」を発売、価格政策と宣伝攻勢でヒット商品に育て上げた。しかし危機感を強めた競合企業からリターナブル瓶の共用を拒まれるなど、苦境に立たされ、最終的にビール事業は売却されるに至った。
創業以来、信治郎が強い思いで根付かせてきた洋酒文化は、高度経済成長とともに広く浸透、ウイスキー事業は順風満帆だった。しかしこの状況に安住せず、社内の緊張感を高めるためにも二代社長の佐治敬三は最難関のビール事業に挑戦する意志を固める。父・信治郞も「やってみなはれ」と背中を押した。
やるからには日本になかったビールをと、社員と共にデンマークに製造・販売に関するノウハウを学びに行った。そしてついに63年4月、徹底した微生物管理の下でつくられた日本発の生ビールを発売、寡占化していたビール業界に風穴を開けるべく挑戦を開始した。
最初は朝日麦酒の販売網を借りて売り出すも、苦戦は続いた。しかし、ここで撤退することなく粘り強く戦い続けたことが、後にプレミアムビール市場の開拓と悲願の黒字化達成へとつながっていくのである。

ここまでのサントリーは基本的にトップダウンスタイルだった。創業期や市場が拡大した高度成長期では、社長の強いリーダーシップで引っ張っていくスタイルで会社が上手く回ったからだ。
だが1990年代前半には会社が大規模化して事業分野も広がり、そのスタイルには限界が訪れた。
そこで三代社長の鳥井信一郎は、各部署が自立自走、つまり自らで判断し自らが責任を取り仕事をする態勢への転換に取り組んだ。
「昔のサントリーは惑星型の組織でした。太陽の光を受けて光っていたのです。これからは自分で光を発する恒星型の組織に変えていきたいと思います。しかも連星型の組織に」
当時「BOSS」「デカビタC」などのヒット商品が続いた食品部門では、若手の活躍が顕著だった。若手は過去の成功体験へのこだわりがないので、営業・生産の第一線の感覚をもとに、現場の情報をいち早く吸収・咀嚼し、それを営業活動や生産活動に結びつけていた。
「社内に聞くな、市場に聞け」
信一郎は、食品部門躍進の原動力となった現場主義を、全社に徹底させていった。
また、信一郎はLET(Listen,Encourage,Trust)の考え方を大切にしていた。Listenとは虚心坦懐に先入観なしに広く意見を聞く、部下の話を熱心に聞くこと。Encourageとは労するところをよく知ってよくねぎらえ、すなわち失意逆境にある人を務めて引き立てろということ。Trustとは信頼して人を使わなければならない、誰でも長所があるのだから信頼して長所を生かすことが大事だ、と考えていた。こうした信一郎の姿勢は、連星型組織へと変貌するサントリーのリーダー像となっていき、大企業になってもやってみなはれ集団であり続けるための礎となった。
「まかせっぱなしはだめだが「まかせる」ことが基本であるべき」
日本製ウイスキーは戦前からアメリカに輸出していたが戦争で途切れたため、本格的には1962年から販売を開始した。当時、味への評価は高かったが、販売量は伸びず苦戦を強いられていた。 79年サントリーインターナショナル社長に就任した佐治信忠は、多様な銘柄のあるアメリカで和製ウイスキーを選ぶ積極的な理由が消費者側にないのが主原因と分析、すでに手は尽くしたと判断し、思い切ってウイスキーの販売原資をすべて前年78年からアメリカで販売していたメロンリキュール「MIDORI」に充てる決断を下した。20年近くウイスキーで苦労し、特に思い入れも強かった現地社員は強く反対。だがそれも押しきり「MIDORI」に賭けた結果、ほどなく「MIDORI」はアメリカでの輸入リキュールトップ5入りを果たし、現在もロングセラー商品の一つとなっている。

(アメリカ)
ペプコム社買収を皮切りに、佐治はサントリーのM&A戦略と海外戦略をほぼ一貫して担当、数多くのM&Aを実行しグローバル化を推進してきた。近年ではニュージーランドのフルコア社、フランスのオランジーナ社、英国老舗ブランドのルコゼードとライビーナ、さらに2014年5月には米ビーム社を買収、サントリーは真のグローバル企業へと変貌を遂げようとしている。
「サントリーが志向するグローバル化は、単にM&Aなどで企業規模を大きくすることではありません。
社員一人ひとりがグローバルなビジネス感覚や能力を身につけて、世界で通用する商品を生み出すとともに、世界で活躍する人材の集まりになるということです。そうでなければ、真のグローバル企業とは言えません」


RECOMMENDED CONTENTS
サントリーをより深く知る









































