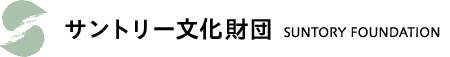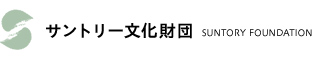成果報告
2023年度
新たな時代の東アジア食文化論の構築
- 東京大学東洋文化研究所 助教
- 上田 遥
食文化研究の父・石毛直道が「東アジア食文化論」を提唱してから半世紀が経過した今、その成果を総括しつつ、現代課題の解決に直結する学問へと開いていかねばならない。こうした問題背景をもとに、本研究では以下3つの課題に取り組んできた。
第一に、石毛直道の著作(『自撰著作集(一二巻)』)を再読分析した。1970年代のフランスでは食文化研究が歴史学(アナール学派)、社会学などで勃興していたが、石毛が「雑学から学際的研究へ」と昇華させた食文化研究もそれに匹敵する学術的水準に到達していた。今西錦司や梅棹忠夫の知的系譜(および東アジア食物史の大家・篠田統)を継ぎながら、「文明の食生活史観」ともいうべき学的体系を構築したことは石毛の顕著な功績であった。しかし、多くの課題も同時に残されていた。その主たる制約は、従来の研究が特定食品の起源や伝播の歴史学・人類学的探求を中心としてきたことで、近代以降(特に戦後)の食文化発展の研究、理論的把握が後回しにされてきたことである。もちろん、石毛自身も優れた食の近代化論を展開しているが、それが社会学的・経済学的に基礎付けられていたとは言い難く、「食の近代化論」の刷新が新たな時代の東アジア食文化論に求められている。分析成果の第一弾は国際誌Int. J. Asian Studiesとして論文掲載された。しかし、日本独自の近代化論(柳田國男など)の枠組みでもっと内在的に石毛の食思想の意義を汲み取るべきことなど、本論文では不本意な点が残されている。論文掲載後も引き続き石毛研究に取り組んできた。
上記の理論研究と併行させる形で、食のwell-being(善き食生活)、お茶の総合研究という2つの実証的テーマを掲げて、東アジア比較研究を実施してきた。
東アジア食文化論の実証的試みの一つとして、現代東アジアにおける食事モデル(食事内容・回数・場所・時間・品質など)の比較分析を実施した。利用データは、研究代表者(上田)が直近5年間で実施してきた日本・台湾・中国・韓国4カ国でのアンケート調査に基づく(各国1,000名20-60歳台)。各国の食事モデル、とりわけ欠食、孤食、外部化、簡素化、早食い、遅延化など「崩食(規範と実態の乖離)」を比較指標とした。崩食とは、「食の再帰的近代(reflexive food modernity)」すなわち食規範を喪失した状態およびその再構築過程にあることを示す典型現象である。分析の結果、崩食は各国でも認められたが、各国の食の近代化経験の差異が崩食の程度や内実に影響を及ぼしていた。台湾は、食規範および食生活実態いずれも変容が大きく、「食の圧縮近代」の典型であった。日本は、実態は変化するものの「家族の戦後体制」に支えられた食規範が強く維持されており、こうして規範と実態の乖離が大きくなることが「食の半圧縮近代」経験そのものであった。韓国は一方で「食の圧縮近代」、他方で「食の半圧縮近代」、すなわち台湾と日本の中間的位置にある。これらの3カ国とは対照的に、中国における崩食はまだ萌芽的実態にあり、将来的に異なる「食の近代化」が生じる可能性が示された。こうして再帰的近代化、圧縮近代化論者が主張する「近代化の複数性」を実証したことが、本研究の主たる成果であり、国際誌Appetiteに論文掲載された(国立台湾大学Chiu教授共著)。
もう一つの試みとして、オーソドックスな品目別分析ではあるが、食文化として深みのあるテーマである「茶」を選択した。経済史家・角山栄が名著『茶の世界史』(1980年)において、近代資本主義社会における「文化から商品へ」という経路を見事に描いていた。これを受けて、本研究では、日本(宇治茶)・中国(武夷岩茶、安渓鉄観音など)・台湾(凍頂烏龍茶など)・韓国(宝城)の現地実態調査を通じて、「商品からふたたび文化へ」という戦後社会経済史を描こうとするものである。中国・台湾・韓国の3カ国ではいずれも、1970年代のナショナリズム運動および国内茶消費市場の開拓を目的として「茶文化」が創出された。日本の茶道を参照しつつも、各国独自の社会思想を複雑に統合した茶文化である。茶文化復興運動のみならず、茶業・経済的動機としても、茶の文化性(テロワール、原産地呼称など)を形成し、茶農家や茶商の付加価値を制度的に保護する仕組みが求められるようになっている。成果の第一弾として論文「宇治茶のフードシステム」を国内誌に投稿したが、より包括的な成果は2026年刊行予定『茶の東アジア史』(NHK出版会)に収録される見込みである。なお、サントリー文化財団中間報告会をきっかけに熱意ある編集者との出会いが生まれたことをここに付記しておく。
2025年5月
現職:東京大学大学院農学生命科学研究科 助教