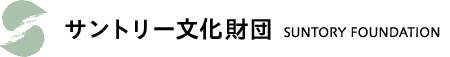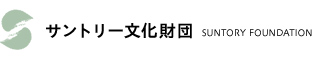成果報告
2023年度
明治・大正期における日本陸軍の組織管理:中央と現場を中心に
- 東京大学大学院法学政治学研究科 博士課程
- 周 文涛
昭和戦前、戦時期には、日本陸軍は様々な下剋上事件(二・二六事件など)、独断の軍事行動(張作霖爆殺事件、満洲事変など)を引き起こしていた。これらの事件はいずれも、首謀者が部隊勤務の青年将校や参謀であるため、これらの事件に象徴される陸軍の秩序混乱は、軍隊への統制力が低下したことに起因していると言えよう。それに、軍隊への統制力が、必ずしも外部要因に刺激され、短期間に低下したとは考えにくく、長い年月にわたる部隊管理のなか、漸次的に劣った可能性も否めない。こうした背景を踏まえ、本研究は日露戦後から大正期までの陸軍の現場管理の実態を解明すべく、研究を進めていた。具体的には、以下の三つの角度からそれぞれ検討を行い、ある程度の成果を収めることができた。
一
部隊の管理者像への検討。部隊管理の優劣を把握するためには、まず部隊管理者の資質を検討する必要がある。本研究は、平時(戦争がない時期)において、現場部隊長の代表格である師団長(師団制度発足から大正末期まで、補任情報が分かる経験者全員)を分析対象とし、現場部隊、中央行政機関、そしてそれ以外の機関と三つの枠に分けて、各枠における勤務時間を考察することで、師団長の全体像と時期ごとの特徴を明らかにすることができた。師団長経験者の多くは、師団長になるまで比較的豊富な部隊勤務経験を持っていたが、日露戦後の8年間に任官した師団長は、その現場勤務経験が大幅に低下し、代わりに陸軍大学校での修学や海外駐在などの勤務が増えた(1908〜1912年の特徴)。そして1913年以降に任官した師団長の多くが、陸軍省、参謀本部、教育総監部で中堅幕僚(局長、部長、兵監)や各軍学校の教官・校長を務めていたことが部隊勤務を低下させた主たる原因である。官僚の勤務経験を考察したところ、人員管理中心の行政官僚が比較的多数だったが、次第に知識や技術に精通する技術官僚へと入れ替わっていった。それでも、師団長経験者の部隊勤務は依然総勤務時間の四割程度を占めている(平均値)。総じて、師団制度発足当初から日露開戦までは、もっぱら部隊勤務を積み重ねてきた職人肌軍人が多かったが、陸軍将校の学歴化と官僚化が進むにつれて、日露戦後、職人肌軍人が次第に消滅し、現場勤務を一定の水準を維持しながら、中央官衙で軍事行政に携わり、もしくは専門知識や技術を必要とされる技術職に就いたりする経験を持つような師団長が大幅に増え、師団長のキャリアパスは多様化していったといえよう。
二
では、このようなキャリアパス上の変容が師団管理にとって何を意味するか。当時の日本陸軍が直面する課題と、それによって新たに形成されつつあった組織文化を踏まえて評価する必要がある。まず、引き続きロシアを主要仮想敵国とし、平時25個師団、戦時50個師団という野心的な兵力目標を掲げた。他方、風靡する社会主義思潮に影響されないように、兵卒への監視体制をより整えるとともに、絶対服従の観念を兵卒に叩き込ませる。そのために、連隊長以下各級部隊長及び幕僚の役割分担を明確に定めた。しかし、将校の管理への工夫が手薄である。このような軍隊のあり方が、良質な予後備役兵に依存すする側面が強く、そのために、学校教育にも軍隊教育と歩調を合わせさせるなど、陸軍が一般社会に対し要求を出し始めた。総じて、この時期、陸軍は「人」を重視する総力戦体制を構築しようとしたとえいよう。したがって、地方レベルでは、人員管理において比較的に知見と経験を積みやすい行政職経験を持つ軍人を師団長に登用するのは、ある意味では合理性が見られるだろう。
三
では、このような環境と師団長人事配置のなか、実際師団長がどのように師団管理行ったか。本研究では、明治末期から大正初期までの間に、師団長に任官した井口省吾と宇都宮太郎を取り上げ、二人の師団運営を考察した。二人とも、陸大の学歴、海外での駐在歴、そして中央省部での勤務経験を持ち、現場部隊での勤務が短い軍人であるが、砲兵出身で、学者肌の井口は技術や軍事研究に熱心であるのに対し、長年情報工作に携わっていた宇都宮は軍事政治家の手腕を持っている。部隊に臨んだ二人はともに階級を踏まえた管理を推奨し、下級部隊長の職権に干渉しない方針をとり、予後備役兵を重視するという軍全体の方針のもとで、地方に向けて、情報発信に努めていた。一方、両者の相違も少なくない。井口は方針通りに部隊管理を行い、青年将校と接触するのに必ずしも積極的でなく、下級部隊長の決断も十分尊重していた。そして、依然師団内の研究会への参加に熱心であった。宇都宮は方針こそ同様であるが、実際に青年将校との接触に意欲的であり、部下の転職のために奔走したり、生活の面倒を見たりし、人情味の溢れた師団運営を行っていた。地方への発信についても、招待されて、小学校生徒などに向けて、機械的に日本国体の宣伝をする井口に比べ、宇都宮は幕僚時代に培った知見を活用し、自らの国際情勢に対する見解を積極的に師団内外に発信し、そのために自ら宣伝の担い手を物色したり、新聞記者を活用したりし、柔軟かつ能動的に振る舞っていた。
課題
この二種類の師団管理を通して全体の師団管理の実態を俯瞰するには、事例の数を増やし、検討の時期をさらに伸ばす必要もある。そこで、昭和初期までの師団長経験者のキャリアパスを分析し、同時期の師団長の師団管理の事例を探すという課題が浮上してくる。同時に、歴史学のみならず、本研究は軍隊管理を題材としているので、歴史学だけでなく、師団管理の事例を組織学の俎上に乗せる際、どういったような新たな観点が生まれるかが期待に値するものである。そのためには、本研究は組織学の知見を導入することを検討したい。
2025年5月