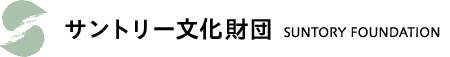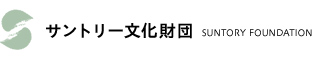成果報告
2016年度
20世紀中期の<蠕虫>をめぐる文学的想像力についての比較研究:乱歩からベケットまで
- 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
- 清水 さやか
研究の目的と内容
蛆虫や芋虫、ミミズなどの蠕虫類を見て、おぞましいと感じる人は少数派ではないはずである。ぬらぬらと蠢くむき出しの身体は、我々人間の姿とかけ離れており、清潔な都市生活に慣れきった人々の目には、それはいかにも不気味に映ることだろう。蠕虫に対する否定的価値づけは現代にはじまったことではなく、たとえば西洋文化圏では、蠕虫は伝統的に死や堕落、貧乏や不衛生、醜悪さなどの概念と結びつけられ、忌まわしいものとして表象されることが多かった。
しかしながら20世紀半ば頃、こうした蠕虫たちは文学において、突如旧来とは異なる形で姿を現すようになった。すなわち、蠕虫は同時代の作家たちによって、人間自身が変身した姿、あるいは「私」という意識が受肉化した姿としてイメージされるようになったのである。では、なぜほかでもないこの時期の文学において、蠕虫は人間あるいは「私」そのものの姿としてイメージされるようになったのだろうか。
その問いに答えるため、報告者はサミュエル・ベケットの小説『名づけえぬもの』やルイ=フェルディナン・セリーヌの諸作品、あるいは江戸川乱歩の短編小説「芋虫」等、蠕虫(ないし蠕虫のようなもの)のイメージが登場する文学テクストを取り上げ、それらを歴史や文化史のなかに位置づけたうえで分析し、比較検討を行った。
研究によって得られた知見
報告者は当初、とりわけ世界大戦およびジェノサイドの経験、そして人文学における〈主体〉の危機・解体という、20世紀を特徴づける二つの出来事が、蠕虫への変身という想像力の活性化に関係しているという仮説を立てていた。しかし研究を続けていく過程で、報告者の問題意識は少なくとも以下の六つの議論へと発展していった。
第一の議論は、「吐き気」を催させるモチーフとしての蠕虫と、〈主体〉の危機という現象、あるいは実存主義文学との関連性をめぐるものである。無意識の発見、諸科学やテクノロジーの発達、資本主義や帝国主義の増大などが起こる20世紀前半、作家たちは自我そのものが不気味で不快なものであるという感性を確立させていった。その不気味さを表現するため、作家たちは蠕虫という「吐き気」を催させるイメージを欲したといえる。
第二の議論は、蛆虫と言語の関係をめぐるものである。ユダヤ人迫害の歴史に明らかなように、「蛆虫」という言葉は、ヘイトスピーチや侮蔑表現、他者排除のために利用されてきた。しかし、言語(の人間に対する関係)に一種の「寄生」性がみとめられるとしたら、じつは言語そのものが蛆虫のイメージの内部にあるといえるのではないか。反ユダヤ主義者として知られるセリーヌ、あるいは戦時中レジスタンスとして活動していたベケットのテクストにはそれぞれ、蛆虫のイメージと言語との複雑な関係が刻印されている。
第三の議論は、身体と科学の発展に関するものである。19世紀後期におけるジャン=アンリ・ファーブルの登場とそれに伴う生物学の発展を契機に、蠕虫は人間にとって、従来よりも近しく親しみ易い存在へと変化していた。このような生物学等の諸科学やテクノロジーの進歩は、オルタナディヴな身体としての蠕虫という夢想を生みだし、またポスト・ヒューマンをめぐる想像力の母胎となっていく。
第四の議論は、乱歩の「芋虫」を生んだ日本の歴史的・文化的土壌に焦点を絞るものである。東洋的な「虫」観、日露戦争と関東大震災の経験、資本主義の発展とともに花開いた都市の消費文化などが、日本の怪奇幻想文学の隆盛、ひいては乱歩における芋虫への変身という奇想の背景にあるといえる。
第五の議論は、蠕虫に変身するという想像力と、性愛との関わりを考察するものである。性愛とサディスムという主題が展開される乱歩の「芋虫」では、公の領域において大規模な戦争が起こり、私的な空間においてグロテスクな性の営みが展開されるという構図がある。身体は公と私の両方の領域において、肥大した欲望によって損壊・蹂躙され、下等な生物(芋虫)に似た肉塊へと変えられてしまう。しかし、身体はそれと引き換えにあらゆる社会的秩序から脱却することに成功し、人間の欲望に対する批判的まなざしを獲得するに至るのである。
第六の議論は、死者、とくに戦死者と蠕虫のイメージ上の親和性をめぐるものである。乱歩の「芋虫」、あるいはトランボの『ジョニーは戦場へ行った』では、戦争の犠牲者は諸器官を失い、蠕虫的身体へと変身することによって帰還する。彼らはやがて(内的な)喋り声や言葉だけを残したまま、物質性の領域を去っていく運命にあるが、その喋り声や言葉は、幽霊=蛆虫のように生者(生き残った者)に取り憑くものとなる。
今後の課題と見通し
以上の議論によって、蠕虫への変身という想像力が、20世紀ないし近代という時代を考える有効な切り口となりうることを多角的に立証できればと思う。今後の課題は、当初の想定をはるかに超えて膨大になってしまった研究範囲を、引き続きなるべく網羅していくことである。本研究のうちベケットに関する論考は、現在執筆中の博士論文の一部となる予定である。その他の部分についても、博論提出後に発表できるよう準備中である。
2018年5月