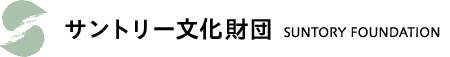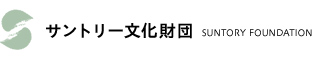選評
政治・経済2025年受賞
『就職氷河期世代 ─ データで読み解く所得・家族形成・格差』
(中央公論新社)
1979年生まれ。
コロンビア大学大学院(GSAS)経済学博士課程修了。PhD(Economics)。法政大学経済学部准教授、横浜国立大学国際社会科学研究院准教授などを経て、現在、東京大学社会科学研究所教授。
著書 『世の中を知る、考える、変えていく』(編著、有斐閣)など。

わが国で、1990年から株価が下落し始め、1991年をピークに地価が下落し始めて、1980年代後半に謳歌した「バブル」が崩壊していった。その影響が新卒採用市場に現れるのは、少し遅れて1993年とされる。新卒就職活動生の間では、最初に影響が出た年は「就職氷河期」、その次の年は「就職超氷河期」、その次の年は「就職超々氷河期」と呼ばれ、就職難が年々深刻化していった。
1993年から2004年に高校、大学などを卒業した世代を就職氷河期世代という。生年でいえば、1970年(1993年に大学卒業)から1986年 (2005年に高校を卒業)が該当する。バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、その後も就業上困難に直面している。本書ではこの世代を、就職だけでなくその後のキャリアパスや家族形成に至るまで、データで丹念に追いながら、その実態に迫っている。就職氷河期世代には、1971~1974年生まれの団塊世代ジュニアも含まれている。人口が多い年代が含まれているが故に、その世代を襲った影響が社会全体に与えるインパクトは大きい。
本書の説得力は、国勢調査、労働力調査、人口動態統計、賃金構造基本統計調査、学校基本調査といった基幹統計を駆使して、就業状況のみならず雇用形態や賃金動向、婚姻や世帯形成などを時系列的に捉えて、就職氷河期世代の特徴を際立たせているところにある。副題である「データで読み解く所得・家族形成・格差」が、本書の内容を見事に言い表している。
本書の刊行時期は、政府が就職氷河期世代の支援策を強化するタイミングと 重なった意味でもタイムリーだし、この世代は年長者だと今や50代に達し、分析できるデータの蓄積も充実してきたという点でもタイムリーだといえる。
著者は、就職氷河期世代を1993~1998年卒を前期世代、1999~2004年卒を後期世代と定義し、その前の1987~1992年卒をバブル世代、さらにその後ろの2005~2009年卒をポスト氷河期世代、2010~2013年卒をリーマン震災世代と定義して、就業状況、年収、出生率などを比較している。比較によると、就職氷河期世代の直後の世代でも、悪化した雇用状況が十分に改善されていなかったという。特に、初職が正規雇用だった人の割合が下がっていた。ただ、正規雇用割合は卒業後の年数を経るにつれて世代間の格差はなくなっていくが、年収の格差は年が経っても縮まらないことを、本書で浮き彫りにしている。このように就職氷河期世代を、1つの世代として独立的に分析するのではなく、前後の世代と比較する手法によって何がどのように違うかをあぶり出すことで実態を解明している。
本書によって新たに明らかにした点は、同じ就職氷河期世代でも、団塊ジュニア世代が属する前期世代よりも後期世代の方が40歳までに産む子供の数は実は 多かったことである。就職氷河期後期世代では、若年期の雇用状況がとりわけ 厳しかったにもかかわらず、出生率が下げ止まっていた。通説を覆す新事実である。
近藤絢子氏は、女性労働経済学者として、国際的にも高く評価される研究を次々と発表している。本書では分析に基づいた政策提言も打ち出しており、今後は学術研究のみならず、社会にも還元する経済学者としても活躍を期待したい。
土居 丈朗(慶應義塾大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)