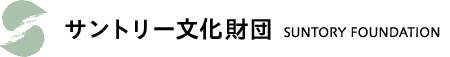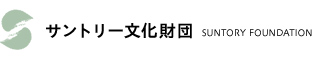選評
思想・歴史2024年受賞
『私が諸島である—カリブ海思想入門』
(書肆侃侃房)
1987年生まれ。
西インド諸島大学モナキャンパス英文学科MPhil/PhD program修了。
慶應義塾大学法学部非常勤講師などを経て、現在、千葉工業大学未来変革科学部助教。
論文 “Peasant Sensibility and the Structures of Feeling of 'My People' in George Lamming's In the Castle of My Skin”(Small Axe, Vol. 27, Number 1(70))など。

「現代思想」なるものをかりに地図のかたちで思いえがこうとするとき、その世界地図にはいたるところに欠落があり、空所があり、空白がある。たとえばアフリカ大陸の大部分がそうした空所となるだろう。また南アメリカのかなりの地域も地図上の空白をかたちづくることになる。これに対してヨーロッパの一部たとえばフランスの思想地図には、ほんのちいさな河川や、丘にもひとしい地上の突起まで描きこまれて、地表のわずかな変容すら自然史的な一大事件であるかのように喧伝され、地図はせわしなく更新されてゆく。
カリブ海に浮かぶ島嶼も、私たちの「世界地図」における欠落部分である。すくなくとも本書の登場以前には、ほとんど白地図にひとしい状態であったと言ってもよいのではないだろうか。現代思想の地理的な布置にかんする私たちの「常識」を、本書は大きく塗り替えてゆく。その意味で、『私が諸島である』という奇妙な標題を与えられたこの書は、かぎりなく挑戦的で、私たちを挑発しつづける。
カリブ海文学を専攻し、西インド諸島大学で博士号を取得した著者は、留学当初、カリブ海文学をハイデガーやラカンといった思想家をとおして分析することを目ざしていたよしである。草稿を見せたとき、指導教員のエドワーズ教授は「なぜハイデガーでなければならない?なぜラカンでなければならない?」と問いかけたという。そこにはおそらく、著者自身も自覚していなかった「西洋中心主義」があった。カリブ海にも「ハイデガー」が生まれ、ハイデガー批判も展開され、ラカンにも比すべき独自な理論が誕生している。カリブ海でも独創的な思想が育まれて、世界を読み、世界を読みかえ、世界をつくりかえようとしている。それはカリブの文化と思想の「クレオール」性を刻みこまれ、そのクレオール性を、むしろ利点ともしてゆく思想である。その思想はまたどこかに到達しようとする思考の暴力性をまぬがれ、他者を「標的」とすることなく、むしろ他者を抱きとめ、他者と共にカリブの海に浮かび、潮の干満に揺られて海の只中にたゆたいながら、他者とたがいに手を取りあうことを可能とする思考である。開放的で流動的な生のかたちを、あたかもそれ自体が水鏡であるかのように、カリブ海は映しとっている。そこに流れているのは、たとえばギリシアという起源の民族、ゲルマンの森という誇り高い始原を有して単線的に流れてゆく時間ではなく、カリブ海に立つ波の動きを移しているかのように、複雑なリズムを刻みつづけて展開されてゆく複線的な時間なのである。
1492年に生起した事件、コロンブスによるいわゆる「発見」以来、西洋近代の剥き出しの暴力にさらされつづけ、搾取されつづけてきたカリブ世界は、以後400年にわたって、民族の絶滅を目撃し、過酷な奴隷制度や年季奉公制を経験してきた。そのカリブ海でこそ、白色人種を人間と等値し、ヨーロッパを世界そのものとみなす思考に抗し、流動性と混淆性とを高唱する思想が編みあげられている。それだけではない。そこでは現在、フェミニズムやクィア・スタディーズすら、自生的なかたちで創造的な展開を見せている。そうした事実を生き生きと伝えてくれる本書は、この国の人文学にあってもっとも重要な文献のひとつとなると言っても過言ではない。
熊野 純彦(放送大学特任教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)