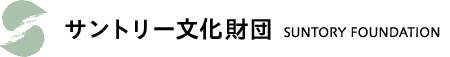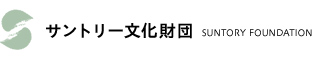選評
芸術・文学2016年受賞
『越境と覇権 ―― ロバート・ラウシェンバーグと戦後アメリカ美術の世界的台頭』
(三元社)
1973年生まれ。
イェール大学大学院美術史学科博士課程修了(美術史学専攻)。Ph.D.取得。
日本学術振興会特別研究員、大阪大学大学院人間科学研究科グローバルCOE特任助教などを経て、現在、神戸大学大学院国際文化学研究科准教授。
著書:The Great Migrator: Robert Rauschenberg and the Global Rise of American Art(The MIT Press)、『油彩への衝動』(共著、中央公論美術出版)など。

ロバート・ラウシェンバーグについて私は長く否定的な評価をしてきた。個人的なことを書くのは、それがおそらく日本のみならず世界においても一般的な評価ではないかと思われるからである。ケージとカニングハムが音楽と舞踊において成し遂げたことに対して、最終段階でラウシェンバーグがたんなる美術家を越えた関わり方をしたために、音楽、とりわけ舞踊に関しては、アメリカはヨーロッパに半世紀の遅れを取ることになったというのが一般的な評価であるといっていい。モダンダンスはアメリカに属するがコンテンポラリー・ダンスはヨーロッパに属する。ラウシェンバーグが舞台芸術に対して根源的すぎる問いを提出した結果、そういうことになったのである。おそらく同じことは音楽にも美術にもいえる。領域を超える問いを安易に発することは基盤そのものの破壊を招く。
この見取り図はとりわけ舞踊に関していまも妥当すると思うが、しかし、池上裕子氏の『越境と覇権』を読んで、私のラウシェンバーグに対する評価は180度違ってきた。サンダースのCIAの文化政策をめぐる本や、マルキスのグリーンバーグ評伝などを読んで、20世紀においていかに政治が文学芸術に直接的に介入してきたか思い知らされたが、池上氏の著書はそれらとはまったく違った視点から、ラウシェンバーグの仕事の意味を浮き彫りにしている。これは、サンダースやマルキスの本が1950年代に重点を置くのに対して池上氏の本が60年代に重点を置いていることの必然的な結果かもしれない。時代の違いは大きく、この違いは当時のパリ、ニューヨークの現地感覚を持たないと理解できないと思える。ある意味でラウシェンバーグは時代遅れの眼でその先進性を批判されていたとも言えて、私の先入見がいかにアメリカや日本の美術関係者の影響下にあったか、よく分かった。ラウシェンバーグはアメリカの覇権を体現しているのではなく、その覇権の批判を体現しているのだ。結果的に彼は、政治が芸術を論じるのではなく芸術が政治を論じるべきだといっているに等しい。
池上氏は、ラウシェンバーグが世界的な評価を得てゆくうえで決定的な契機となった1960年代前半のパリ、ヴェネツィア、ストックホルム、東京という四つの都市の美術界の状況を克明に浮かび上がらせることによって、第二次大戦後、美術の中心がパリからニューヨークへ移ったということの意味を教える、というより、そのことの意味をほとんど読者に突きつけるようにして、再考を促しているのである。とりわけ、1964年のヴェネツィア・ビエンナーレでラウシェンバーグがグランプリを獲得してゆく背景を、アメリカ館のコミッショナーをつとめたアラン・ソロモンを中心に描き出してゆく過程は圧巻で、パリに対する対抗意識はヴェネツィアのほうにこそ強く、アメリカ本国にはむしろ戸惑いのほうが強かったというような意外な事実が次々に明らかにされてゆく。半世紀を経てようやく全体像が見えてきたとの印象が強い。
とはいえもっとも重要な点は、その過程で「ダンテ・ドローイング」などラウシェンバーグ自身の作品の魅力の中心がどこにあるか――そのひとつが時代を呼吸する芸術だ――浮き彫りにされていることで、今後の美術批評のあるべき座標を見事に示していると思える。本書は6年前に刊行された英文著書を著者自身が翻訳したものだが、個人的には日本語版にいっそうの好感をもった。
三浦 雅士(文芸評論家)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)