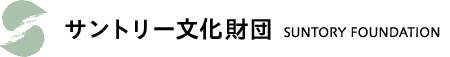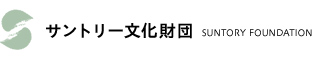選評
思想・歴史 2015年受賞
『対華二十一ヵ条要求とは何だったのか ―― 第一次世界大戦と日中対立の原点』
(名古屋大学出版会)
1975年生まれ。
京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了(政治学(日本政治外交史)専攻)。博士(法学)。
京都大学大学院法学研究科助教授を経て、現在、京都大学大学院法学研究科教授。
著書:『加藤高明と政党政治』(山川出版社)、『「八月の砲声」を聞いた日本人』(千倉書房)。

対華二十一ヵ条要求が戦前日本外交の失策だったことは、近代史に関心のある人であれば誰でも知っている。これまでにも数多くの先行研究が存在するが、政策決定、交渉過程、国内状況、そして国際環境のすべてを包括的に分析した業績は少なかった。「希望条項」とされたにせよ、なにゆえ、最終的には取り下げざるを得ないような、中国の主権をあからさまに無視するかのような条項まで要求にもりこんだのか。しかも、後に幣原喜重郎を自らの政権の外相に起用し国際協調路線をとった加藤高明が、なぜ日中関係をおかしくするような交渉を自らの外相時代に行ったのか。このような疑問は、これまでにも有力な仮説は存在していたものの、なかなか解消されなかった。本書は、膨大な史料渉猟を経て、対華二十一ヵ条要求について、現段階で達成しうる最も包括的な分析を行った業績であると高く評価できる。
結論は穏当であり、そのようなことだったのだろうと思うが、日中関係とその後の日英関係などに与えた影響を考えると悔やまれる出来事であった。帝国主義時代の外交官としては比較的穏健な考え方の持ち主であった加藤高明であったが、彼は、自らの政治家としての野心から国内の対中強硬策にのってしまった。もともとこの問題については慎重だった山県有朋などの元老を、外交一元化の方針のもと政策決定から排除し、山県に陸軍を説得してもらうこともなかった。さらに日露戦争直後とは異なる中国情勢や欧米の国際政治観の変化をも見誤り、欧米諸国に対して、問題をはらむ「希望条項」について通報することを怠った。この点を袁世凱政権からリークされて、情報戦において劣勢にたたされてしまった。最終的に、外には英米からの批判、内からは元老からの批判を受けて、「希望条項」削除したうえで最後通牒を発することになった。結局、中国に要求事項を受け入れさせることには成功したが、日本が当時としても露骨な帝国主義政策をとる国であるという見方を国際社会に与えてしまった。これが、評者の理解したところの本書の分析である。
おそらく対華二十一ヵ条要求それ自体の研究として、本書を超える包括的分析を行うことは困難であろう。そう評価したうえで、なお残る疑問は、対華二十一ヵ条要求がどの程度決定的な失策であったか、ということである。著者は、加藤自身「内心では忸怩たるもの」があり、その反省から自ら政権をとったときは国際協調路線をとったと語り、1920年代には、「まだ友好を取り戻そうとする復元力が働いていた」という。しかし、そうだとすると、対華二十一ヵ条要求というのは、一つの政権の戦術的失策であって、かえって後の教訓になって良かったという程度のものになってしまうのだろうか。1930年代の日本の侵略につながるプロセスへの決定的事態は、もっと後の時代に起こったのだということになるのだろうか。もちろん、そうかもしれない。著者も「二十一ヵ条が原因となって、取り得る選択の幅は相当狭められた」という。いったい「選択の幅」は、いかなる構造のなかでどの程度狭められたのであろうか。このあたりについての著者の考えを聞きたいものである。
田中 明彦(東京大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)