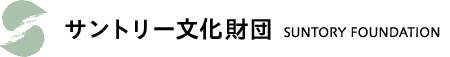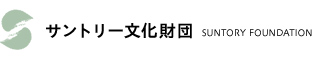選評
社会・風俗 2012年受賞
『北の無人駅から』
(北海道新聞社)
1968年生まれ。
大阪府立北野高等学校卒業。北海道大学文学部行動科学科を中退後、北海道内を中心に活動するフリーライターとなる。道内市町村・郷土関係の出版物などに多くの共同執筆作をもつ一方、ノンフィクション作品の取材執筆活動を行っている。
著書:『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社)

本書はこの部門では、最も「読ませる」力作と思った。著者には繊細で深い観察力、そして民衆への温かい心がある。また、渾身の力が感じられた。それゆえ選考会で私も高得点を与えた。しかし同時にこの本には問題点も感じたし注文もあると述べたら同意を受け、ならば選評を書けということになった。そこで率直に、唸らされた点と問題点を述べたい。
本書は、北海道の無人駅を起点に、多くの無名の人たちの生き様を、直接の聞き取りや資料調査で微に入り細にわたって描いたものだ。主題や対象はきわめてローカルかつマニアックで、誰が読むだろうかと著者は悩んだという。しかし、特殊なミクロの世界もとことん穿てば、宇宙に通じる。本書の魅力は、名もない庶民の心の襞に深く分け入って、そこに豊かな宇宙を見出していることだろう。
最初からグイグイ引き込まれる。酔って列車に轢かれ両足を失ったアイヌの文太郎が、もの凄い気力と体力、漁の腕前により、文字も読めないのに「アタマのええ」船頭として清水次郎長的な親分になる話。よそ者である都会人の自分勝手な「自然保護」の意識とはまったく違う感覚で、信念を持ってタンチョウやオオカミを相手に暮らしている「頑固な変人」たちとの心温まる交流。陸の孤島の漁村に道路が通じて変わる漁民たちの生活と心。また、こういう地元の人たちに、心を開いてもらうまでの涙ぐましい著者の努力。
われわれが上からの目線で切り捨てる世界を、このように愛情をもって魅力的に浮き彫りにする作者の力量は、単に優れた観察力や文章力ゆえではなく、彼の人間性ゆえでもあろう。本書を読んですぐ思い出したのは、民俗学者宮本常一の名著『忘れられた日本人』だ。宮本と同様、本書も、地方の人たちの生活と心に関する貴重な時代の証言だ。そして、この証言には渡辺の個性が深く刻印され、他人には書けないものとなっている。途中に沢山挿入されている、辞典的な解説のページも懇切でスグレものだ。
次に問題点を指摘したい。個別のミクロ世界も、確かな眼で穿つと、自ずと普遍の世界につながる。しかし、意識的に普遍化しようと安易に理屈や論に走ると、一挙に生彩を欠く。本書でも、本来の手作り的な「有機農業」と北海道の「クリーン農業」の違いに関連して、農業指導員の苦労話などを具体的に語るのは面白い。しかし、その先に進んで著者の農業政策論、TPP論などに及ぶと、たちまち平板な紋切り論になり個性が消える。町村合併の話についても、住民投票論から「そもそも民主主義とは」といった政治論に進み、合併は「国の政策誘導に乗せられた」などと論じているが、これもまたありふれた定型論だ。政策論、政治論に走った章では、人々の生活や心を見る眼も格段に粗になっている。理論で勝負するというなら別だが、宮本常一が一般化を敢えて禁欲した意味を著者はしっかり噛みしめて欲しい。これは、著者の今後の成否を左右する問題である。一般受けする紋切り論、定型論でポピュラーになって欲しくないが故の注文だ。
最後になったが、この書を引き立て生彩を与えているのは並木博夫の写真だ。グラビア用紙にしないで、普通の頁にさりげなく印刷されている地味な風景が、主題にも合い、かえって自己主張が感じられる。空気感という有り体の言葉は避けたいが、独特の味わいを感じさせる写真だ。写真家並木氏も共同受賞者と言えるだろう。
袴田 茂樹(新潟県立大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)