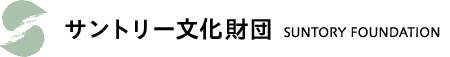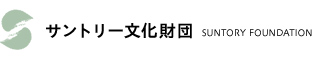選評
社会・風俗 2007年受賞
『生物と無生物のあいだ』
(講談社)
1959年生まれ。
京都大学大学院農学研究科後期博士課程修了。京都大学農学博士。
日本学術振興会特別研究員、京都大学助教授などを経て、青山学院大学理工学部化学・生命科学科教授。
著書:『プリオン説はほんとうか?』(講談社)など。

「生物と無生物のあいだ」は、生きものに本当に興味を持ち、それに正面から向き合った人には、かならず浮かぶ疑問である。かつて同じ表題の書物があったはずである。
でもその疑問を持ち続ける人は少ない。いわゆる専門分野に入ってしまうと、木は見るが、森は見なくなる。木を精細に見ることが成功を意味するような学界が、社会的に成立しているからである。
著者は細胞生物学の若き学徒として、アメリカの研究室に赴く。そこでさまざまな人に出会い、さまざまなことを学ぶ。そこに描かれる人々の群像が、読み手を強く引きつけてしまう。
叙述が生きているのは、それが著者自身の体験に発しているからである。自分が学んできた過程を通じて、現代生物学の歴史を読者に伝えること、これはできそうで、なかなかできない。科学は客観性の名において、しばしば個を消そうとするからである。教科書的という言葉が生まれる所以であろう。しかし学問は結局は個人が背負う。世に思われているように、学界が背負っているのではない。
理科系ではない選考委員から、文章がいい、品があるという評があった。その通りだと思う。適度の抑制を効かせ、しかも感情(熱情?)をまじえて語るのは、科学の分野では簡単にはできないことである。著者のその面での才能は貴重である。これまでの著作だけではなく、今後の活躍が期待される。
この本に登場するパラーディに、私は日本で二度会ったことがある。最初のときには、私は大学院の学生だった。一緒に箱根や鎌倉を旅し、わずか数日とはいえ、多くのことを教えられた。ただし生物学の話は一切していない。第二次大戦の帰結に話が及ぶと、パラーディは急に能弁になった。連合軍はあそこまでドイツを追い詰めてはならなかったというのである。その人がもはや歴史になっていることを思うと、時代の動きの速やかさを思う。
現代の生物学に欠けがちだったものは、著者が動的平衡と呼ぶ主題である。日本の多くの生物学者は、その欠落に気づいていた。なぜなら日本は西欧型生物学の辺境だからである。そこから見れば、中心に欠けているものが、案外よく見える。「行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。」
日本の生物学者たちは、それをさまざまな別名で呼んできた。中村桂子は生命誌、具体的にはゲノムと呼び、池田清彦は構造主義と呼び、さらに多くの人はシステムと呼んでいる。著者の考えも、大きな意味では、あるいは乱暴にいえば、その流れの中にある。私はそう思う。一つの遺伝子をノックアウトしたマウスは、しばしば「正常に」生きていく。それに驚いた科学者たちは、いつの間にか西欧型の思考に慣らされていただけのことであろう。しかし進化を考えれば、それでよいはずである。たった一つの部品が壊れたら使えない機械に、何億年の命が保てるはずがない。
本書のすべての叙述は、最後の一文に向かって集約していく。これは見事である。「私たちは、自然の流れの前に跪く以外に、そして生命のありようをただ記述すること以外に、なすすべはないのである。それは実のところ、あの少年の日々からすでにずっと自明のことだったのだ。」
養老 孟司(東京大学名誉教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)