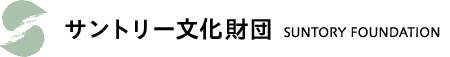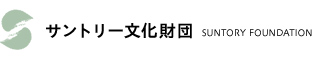選評
社会・風俗 2001年受賞
『太平洋のラスプーチン ―― ヴィチ・カンバニ運動の歴史人類学』
(世界思想社)
1953年、東京都板橋区生まれ。
大阪大学大学院人間科学研究科後期課程退学。
北海道大学文学部助手、フィジー・南太平洋大学社会経済開発学部客員研究員、大阪大学人間科学部助手、オーストラリア・アデレード大学人類学部客員研究員、奈良大学社会学部助教授などを経て、現在、大阪大学大学院人間科学研究科教授。
著書:『経済人類学の危機』(世界書院)、『太宰治を文化人類学者が読む』(新曜社)など。

「ヴィチ・カンバニ」とは、「フィジー・カンパニー」のフィジー語形。それは本来、フィジーの作物を西洋人の手を介さずフィジー人自身の手で販売するための「会社」でありながら、狭義のビジネスをこえ、「フィジー人のためのフィジー」を作ることをめざした経済、政治、宗教、社会をめぐる広汎な運動体となった。この運動の中心となったのが、当時三十代のフィジーの男アポロシ。
口絵写真でまず目に飛び込んでくるアポロシの姿は、そのカリスマ的指導力から西洋人をして「太平洋のラスプーチン」と呼ばしめたイメージにはあまりそぐわぬ、「背が低く風采が上がらず」(当時の証言)という印象なのだが、「平民」と自称し、又みなされたアポロシが、伝統社会の権力者であった大首長たちを凌ぎ、いかに人心を掌握して西洋人支配の脅威となるほどの力をつけ、「フィジーの王」とまで讃えられるようになったか ― その経緯を、本書はあたかも一篇のドラマのように鮮やかに描きだす。
しかし、本書は決して過剰な感情移入や特定のイデオロギーのもとに描かれた文学的叙述に流れていない。あくまでも冷静な筆致を保ちつつ、「歴史とフィクション、学問と想像力の文節性を駆使」し、「ポストモダンの極論にも啓蒙主義的なナイーヴさにも染まることなく、喚起力に溢れた物語を紡ぎ出す」という明確な方法論的自覚に貫かれている。
出典の明示や引用の多用を心がけ、「証拠」と「可能性」との絡みあいを提示したという本書の叙述の姿勢は、資料そのものに語らせることを意識したホイジンガの名著『中世の秋』の歴史叙述の姿勢にも通じる。もっとも、ホイジンガの歴史叙述が中世からルネサンスへの比較的緩やかな移行を扱っていたのに対し、本書はフィジーが西洋文明との接触によって近代化、資本主義化の波に直面したダイナミックな歴史の転換点を扱っている。政治史、経済史、事件史から文化史、心性史へという、アナール学派の主導した「新しい歴史」の流れは、歴史叙述の形式そのものにも変容をもたらしたが、本書は異質なものとして扱われがちであった事件史、政治史と文化、心性の議論を融合し、文献調査とフィールド・ワーク、すなわち文字資料と口述資料を同等なものとして統合した上に成立した画期的な「歴史人類学」の成果である。それはまた、一人の「英雄的個人」を通じて歴史の変動を記述するという、「典型人物」「世界史的個人」の叙述の試みともなっている。
圧倒的な規模と持続性と影響力を誇る反植民地的、民族主義的運動としての「ヴィチ・カンバニ運動」は、著者自身が言うように、近代国家と伝統社会の整合性、発展、開発とは何かという現代人類学、ひいては人文科学、社会科学全般に共通する普遍的な問題を提起する。
いまだ全体像がとらえられていなかったというこの運動を、五年間にわたる地道な現地調査により、膨大な未発掘資料および聞き書き資料を駆使して描き出した本書は、十年に一度の労作という選考会の評にふさわしく、緊迫する世界情勢のなか、ますます深く、重い問いを発し続ける。
佐伯 順子(帝塚山学院大学教授)評
(所属・役職等は受賞時のもの、敬称略)